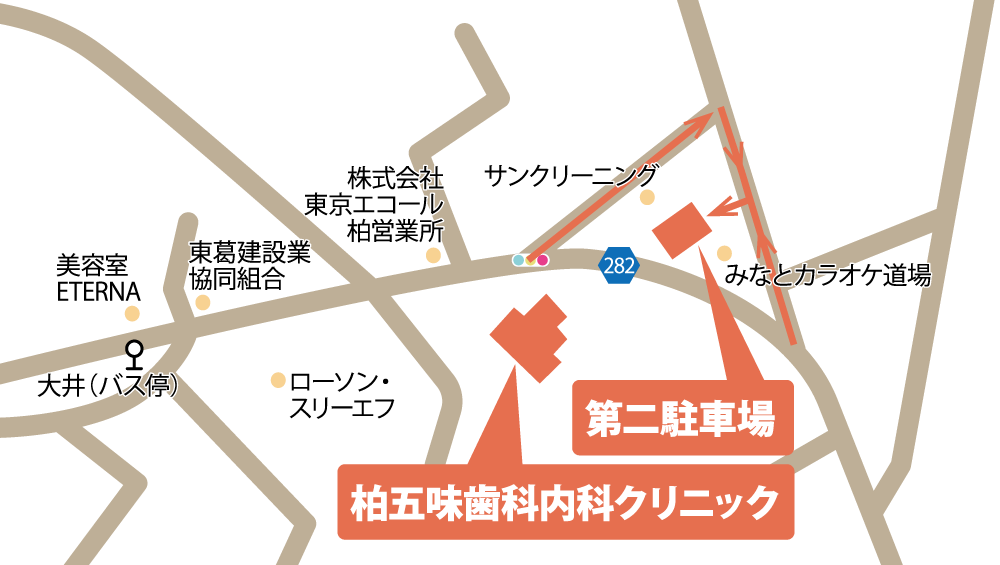主にブラッシングによる磨き残しや口腔内のケアを放置することで、歯の表面にプラーク(歯垢)ができるわけですが、これを放置し続けると次第に沈着し、歯石となります。そこから細菌が発生し、歯周組織に炎症反応がみられるようになります。これが歯周病です。
主な症状としては、歯茎が腫れる、口臭がきつい、歯磨きの際に出血する、歯がグラグラする、歯茎が下がり気味になっている、など様々ありますが、その現れ方というのは、病状の進行程度によって異なります。いずれにしましても、日本人の成人の8割くらいの方が歯周病を発症していると言われています。上記の症状に心当たりがあれば、一度ご受診されることをお勧めします。
なお歯周病につきましては、はっきり同疾患であると特定できる自覚症状というのが、ある程度まで進行しないとみられません。そのため、放置が極限まで続くと、気づいた時には歯がグラグラしていて、抜歯するしか方法がないという状態になっている患者様も少なくないです。
また歯周病を一度発症してしまうと、ご自身でケアするというのは困難です。つまり歯周病の進行を止めることはできないということです。歯周病を治すには、歯科を受診し、ブラッシングだけでは取り切れない、石灰化した歯石などを取り除いて、口腔内環境を清潔にしなくてはなりません。症状がそれほど重くなければ、数回の受診で済みますが、重度な状態だと通院回数も増えますし、費用もかさみます。そのため、どんなにしっかり歯を磨くという方でも半年に1回くらい定期的に受診されることをお勧めします。
歯周病と全身疾患の関連性について
歯周病と聞くと、単なる口腔内の病気と思われるかもしれませんが、全身疾患との関連性も最近は指摘されています。なかでも、糖尿病の患者様は発症リスクが高いとされています。また、誤嚥性肺炎を引き起こす原因菌は、歯周病に含まれる細菌が多いと言われています。さらに、歯周病の原因となる細菌は、歯肉の血管などから入り込んで動脈硬化をさらに促進させます。そして心臓や脳付近の血管の血流を悪化させる、詰まらせるなどすると虚血性心疾患(狭心症、脳梗塞)、脳血管障害なども起きやすくなると言われています。
また妊娠すると歯肉炎に罹患しやすくなるのですが、これを妊娠性歯肉炎と言います。この疾患を放置すると、歯周病が進行することもあるので、しっかりプラークコントロールをしていくようにしてください。なお歯周病は、早産や低体重児のリスクを伴いますので要注意です。
歯周病でよくみられる症状
先ほども触れましたが、以下のような症状がみられるという場合は、歯周病が疑われます。一度ご受診ください。
- 朝の起床時、口内にネバネバした感触がある
- いつも口臭を気にしている
- 歯磨きをしていると歯茎から血がでる
- 歯がグラグラしている
- 歯茎が赤く腫れ、膿も出ている
- 歯が浮く感触がある
- 固いものが嚙みづらい
- 歯間に食物がよく挟まれる
- 以前よりも歯が長くなっている気がする(歯茎が下がり気味)
- 歯が動きやすい、出っ歯になってきた
歯周病などの特徴について
健康な状態の歯周組織や歯肉炎、歯周病の特徴は次のようなものが挙げられます。
健康な状態
歯肉の色が薄ピンクの状態です。
ブラッシングをしても出血がみられません。
歯周ポケット(歯と歯茎の境目で細菌が増殖し、歯茎が下がっていく)がありません
引き締まった歯肉をしています
歯肉炎
歯肉は真っ赤に充血し、歯茎は腫れた状態です。
固いものを食べる、ブラッシングをするという場合に出血がみられることもあります。
歯周病
歯肉は赤紫色をしています。
歯周ポケットが発生し、それによる炎症が慢性化して、骨も溶け始めています。
口臭がみられ、歯が浮いている気がすることもあります。
病状が進行していくと歯根を支えている骨の大半は溶け出し、歯のグラグラも激しくなります。
ブラッシングによって、出血や膿がみられるようになります。
歯周病治療の大まかな流れ
-
1.歯周病検査
歯周ポケット(歯と歯茎の間の隙間の深さ)を測定し、歯周病の進行度、歯石の付き具合 を確認します。合わせて、レントゲン写真を撮影し、骨の状態も確認します。
場合により、口腔内写真を撮影し、患者様の現在のお口の中の状況を一緒に確認していただくこともあります。 -
2.正しいブラッシングを学ぶ
現在のブラッシングの仕方を確認したうえで、磨けていない箇所をチェックし、正しい ブラッシングを身につけていきます。治療後も定期健診の際にしっかり磨けているかの チェックもしていきます。 -
3. かみ合わせの調整など
歯周病は、病状の進行程度にもよりますが、咬合(噛み合わせ)時にかかる歯の力が負担となって、歯周病治療に悪影響が及ぶこともあります。そのため、歯科医師が必要と判断すれば、咬合の調整や歯を固定させるなどして、歯の安静な状態の環境づくり をすることもあります。 -
4.歯垢や歯石を除去
歯周病の原因のひとつでもある歯垢や歯石を除去します。歯石は石灰化(唾液に含まれるリンやカルシウムが混じるなどして起きる)しているので、単なるブラッシングで取り除くことは困難です。さらに歯石があると歯垢(プラーク)が付きやすい状態でもあるので、歯周病をこれ以上進行させないためにも速やかな処置をし、口腔内の衛生環境を整えることが大切です。
使用する器具については、多くの歯科クリニックで用いられている、超音波スケーラー、キューレットスケーラーなどを駆使していきます。 -
5.歯周外科処置(歯周ポケットが深い場合)
歯周病の病状が進み、歯槽骨が多大な損傷を受け、歯周ポケットが深くなっている場合は、スケーラーなどの器具を外から挿入して、プラークや歯石を排除するのは困難です。その際は、歯肉を切り開き、歯根をむき出しにした状態にしてから歯垢や歯石を取り除いていきます。 -
6.歯周組織再生療法も行います
また当院は、歯周病等で歯を支える周囲の組織(骨 など)が失われてしまい、抜歯の可能性が高いができるだけ回避したいという場合に再生誘導剤を使用して、組織を回復させていく歯周組織再生療法も行っています。ただ、場合によっては、効果がみられないこともありますので、ご希望される際は一度ご相談ください。詳細は丁寧に説明します。 -
7.治療後は、しっかりメンテナンス
歯周病の治療が終わっても、歯の良好な状態は引き続き維持していく必要があります。したがって、定期的に歯の検診として、歯科医による口腔内の確認と歯科衛生士による歯のクリーニングを少なくとも半年に1回程度は受けるようにしてください。